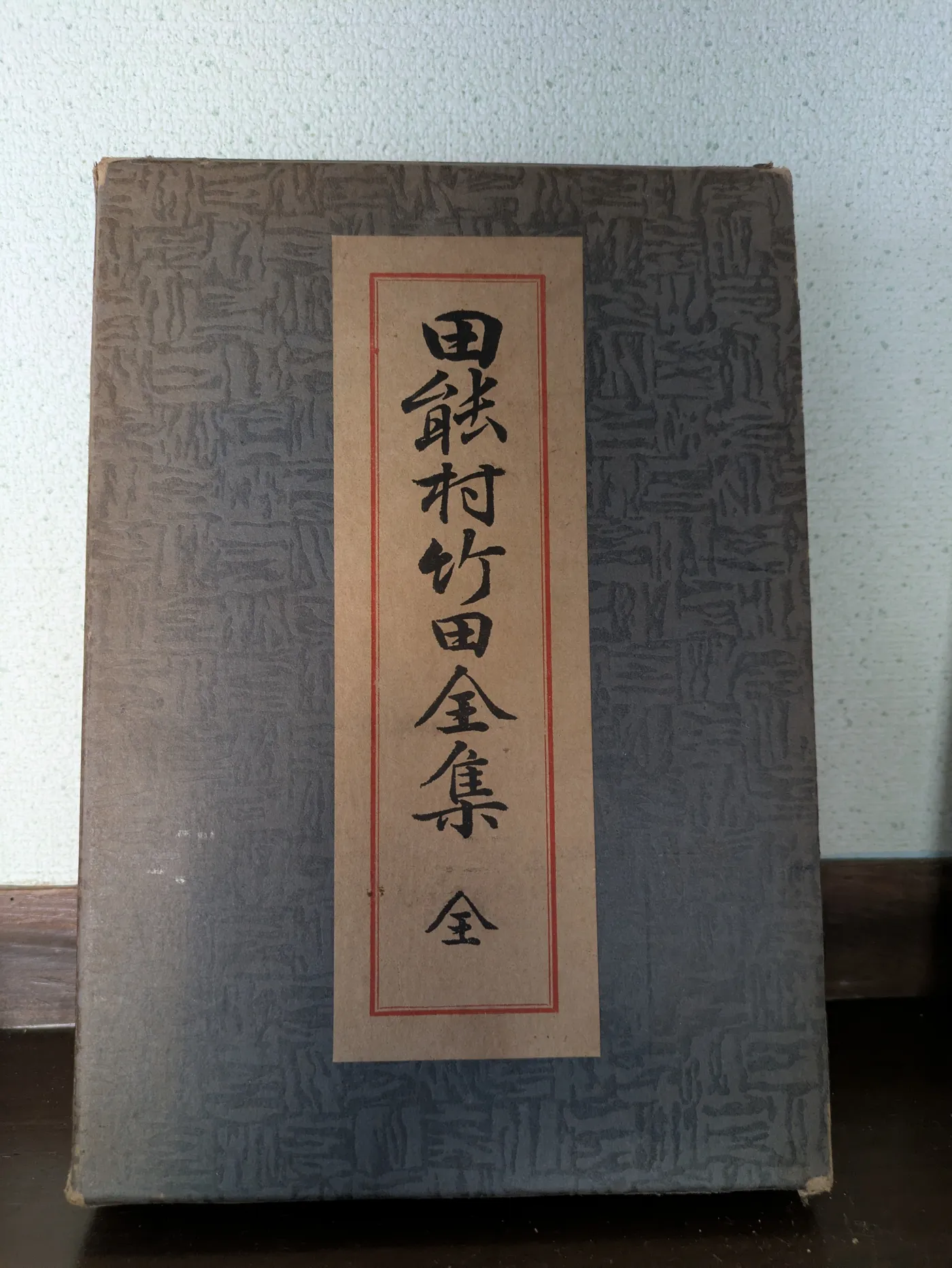豊後の地に生まれた、江戸後期の文人画家
田能村竹田(1777-1835)は、豊後国岡藩(現在の大分県竹田市)の藩医の家に生まれました。幼い頃から学問と芸術に類稀なる才能を示し、藩校「由学館」の頭取を務めるほどの秀才でしたが、武家社会の窮屈さや藩政への失望から、37歳で官を辞して野に下ります。
以降、京や大坂、長崎を旅し、頼山陽(らいさんよう)や浦上春琴(うらがみ しゅんきん)、青木木米(あおき もくべい)といった当代一流の文化人たちと深く交流しながら、詩・書・画に生きる自由な文人としての人生を全うしました。

竹田の美学:「精神」と「品格」の追求
竹田は、単に美しい絵を描くだけの画家ではありませんでした。彼の芸術の根底には、儒学の教えに基づいた高い精神性と、俗世から距離を置く文人の「品格」がありました。
彼の画論**『山中人饒舌(さんちゅうじんじょうぜつ)』**では、「画は士君子の余技(絵画は教養ある人物の嗜みである)」と述べ、技術の巧みさよりも、描く人間の内面や精神性が作品に現れることを最も重要視しました。古人の優れた作品に多く触れることを弟子に説きながらも、最終的には「自家に立脚す(自分自身の表現を確立する)」ことを目指す、その姿勢は彼の芸術思想の核となっています。
生活の芸術としての「煎茶」
そんな竹田にとって、煎茶は単なる飲み物ではなく、日々の暮らしの中で美と精神性を追求するための芸術実践そのものでした。
普通の人は茶を飲むものと心得ているが、あれは間違いだ。舌頭へぽたりと載せて、清いものが四方へ散れば咽喉へ下るべき液はほとんどない。ただ馥郁たる匂いが食道から胃の中へ沁み渡るのみである。 — 夏目漱石「草枕」
竹田は、抹茶の伝統も深く学びましたが、より自由で個人の精神性を重んじる中国の文人文化に倣い、煎茶の道を深く探求しました。彼が29歳の時に著した**『竹田荘泡茶訣(ちくでんそうほうさけつ)』**では、茶葉の選定から水の選び方、湯の温度、淹れ方、そして「得趣(お茶の真の趣を得ること)」に至るまで、9つの法則を体系的に論じています。
技術を超え、一杯のお茶を通して精神的な境地に至ろうとするその姿勢は、まさに彼の芸術思想と軌を一にするものです。絵画も煎茶も、竹田にとっては自己の内面を高めるための、等しく尊い「道」でした。
彼の生き方は、芸術と生活が分断されず、暮らしの隅々にまで美意識を行き渡らせることの豊かさを、現代の私たちに静かに語りかけてくれます。